 
第1話(その2)
ユークリッド・タイラー大将。その名を知らぬ者はこの銀河にはおそらくいるまい。千年帝国の英雄、銀河皇帝の臣にして千年帝国バルディアス方面軍総司令官。幾多の戦場で皇帝の軍を率いて戦い、ただの一度の敗北もない不敗の名将、神将タイラー。彼の前に三度の敗北を強いられたクレティナス軍にとって、彼はまさに天敵であった。
そのタイラーはアルフリートとの戦いを前に表情を険しくしていた。彼の構想した作戦に乱れが生じていたのが主な要因であったが、彼の命令を無視して先行した男に対しての負の感情がその一部を占めていた。
「カルソリーは何を考えているのだ。敵を発見次第、各艦隊が連絡をとって、三方向より同時に包囲攻撃するというものを。勝手に先行されては作戦が台無しではないか」
ディスプレイスクリーンに映しだされるクレティナス軍と帝国軍の位置関係を見て、タイラーは声をあげた。
当初、「バルディアスの門」を出撃した駐留艦隊の戦力は第七、第一九、第三二の三個艦隊であった。第七艦隊をユークリッド・タイラー大将、第一九艦隊をオーエン・ラルツ中将、第三二艦隊をヴァルソ・カルソリー中将が指揮し、タイラーが全軍の総司令官を兼ねていた。ところが、アルフリート率いるクレティナス艦隊の前に姿を現したのはカルソリー中将の第三二艦隊だけであり、タイラーとラルツ中将の艦隊はクレティナス艦隊とは未だ720光秒、およそ六時間の距離にあったのである。
「カルソリー中将は功をあせったようじゃな。神将の名が彼を追いつめたと見える」
通信パネルに白髪混じりの歴戦の勇将といったラルツ中将の顔が映し出され、タイラーに語りかけた。ラルツ中将はすでに六○歳を越えながらも現役の軍人という第一九艦隊の司令官である。タイラーは自分の四倍の戦歴を有するこの人物には常に敬意をはらっていた。
「ラルツ中将、それはどういうことでしょうか」
「わからぬはずはあるまい、タイラー提督」
ラルツ中将の言葉は、タイラーに対するカルソリー中将の心情を指摘していた。
ユークリッド・タイラーは三三歳にして、帝国軍最高の名将との評価を受けていた。帝国軍高級士官学校を第二位の成績で卒業したという経歴をもち、実戦においてもその才幹を大いに発揮して現在の地位に就いたのである。しかし、同時にそれは彼に対する他の者の嫉妬や嫉みの感情を招くことになった。特に、タイラーと同期で、高級士官学校を首席で卒業したカルソリーの目には、彼はライバルではなく完全な敵として映っていた。それゆえ、タイラーも傲慢で自己顕示欲の強いカルソリーに対しては、あまり良い感情を持ち合わせていなかった。
「……ですが、軍隊において勝手な振る舞いは許されません。ましてや彼は十数万に及ぶ将兵の命を預かる身、責任ある行動をとってもらいたいものです」
「しかし、放っておくわけにも行くまい。相手はかの『赤の飛龍』だと聞く。早急に手をうった方が良いのではないかな」
タイラーは記憶の淵からその名前を呼び起こした。
「アルフリート・クライン少将…ですか?」
「そうじゃ。彼が相手では、カルソリー中将にはちと荷が重すぎようて」
神将と呼ばれるタイラーも老提督の言葉にはうなずいた。
「わかりました。できる限りのことはしましょう」
半ばラルツ中将に説得される形でタイラーは応えていた。
通信パネルに映し出された老提督の画像が消えると、タイラーの副官であるアイスマン大佐が不満の声を上げた。
「迷惑な話です。カルソリー提督というお人は……まったく」
「まあ、そういうな。あれでも同じ主君に仕える僚友だ。見捨てるわけにはいかないさ」
自分の心に嘘を言っているなと、タイラーは感じながら苦笑した。
「私の大切な友人だからな」
いつの頃からだろうか。戦争という名の人類史上最悪の犯罪行為が、表面上、一流の演出家による舞台のような美しい光景を描くようになったのは。クレティナス軍と千年帝国軍が衝突したベルブロンツァ恒星系は、各艦隊から放たれた無数の青色の光の帯に彩られていた。暗黒の空間を無秩序なエネルギーの光の矢が飛びかい、衝突が派手な爆発光をあげていた。宇宙標準暦八月一三日、六時一八分のことである。
ベルブロンツァ恒星系を構成する二重太陽の一つ恒星アーメス、この星を背にして横一列に平陣を敷くクレティナス艦隊に対して、千年帝国艦隊は無限に広がる空間を背に平行陣を敷いて応じた。後に「ベルブロンツァ会戦」と呼ばれることになった戦いは、ごくありふれた両軍の長距離ビームの砲撃戦から始まった。
帝国軍第三二艦隊司令官ヴァルソ・カルソリー中将は、艦橋にもたらされた報告に笑みを浮かべた。情報士官によって秒単位で送られてくる情報が整理され、中央の全天空スクリーンに恒星アーメスを背にして布陣するクレティナス艦隊の姿が映し出されていた。
「敵の司令官は用兵を知らないと見える。自らの退路を断って戦うなど自殺行為ではないか。この戦い、私の勝ちだな」
自信にあふれているといえば聞こえはいいが、カルソリーはいささか自信が実力を先行しているタイプの人間だった。彼は高級士官学校時代から戦術理論では誰にも負けたことがなく、教授陣からの評価は第二位のタイラーより高かった。自分が負けるはずがないと彼は常に信じていた。それが不幸にも、彼の自信をして他者の意見を否定させ、敵の力を軽視させる結果になっていた。それに、彼にとっての敵は僚友のユークリッド・タイラー大将だけであり、クレティナス軍のまだ若い司令官など彼の眼中にはなかった。
「失礼ですが……司令官閣下」
カルソリー中将の幕僚であるエンリーク・ソロ准将が意見を述べた。
「敵は、『背水の陣』を敷いているものと思われます。自らを死地に追込み必勝の念をもって前面の敵を破る……四千年の昔、中国の韓信という武将が使った策です。敵は必死の攻撃を仕掛けてくるでしょう。それに、後方からの攻撃を心配する必要がありませんから、こちらへの攻撃の集中が容易なはずです。用心したほうがよろしいのではないですか」
「甘いな。今の時代、士気の高揚だけで戦争に勝てるものか。敵が戦力を集中してくるならこちらも集中するまでだ。数ではこちらの方が多いのだからな。タイラーが来る前に『赤の飛龍』とかいう小僧を葬ってやるわ」
「ですが、ここはひとまずタイラー提督の到着を待ってからの方が……」
エンリーク・ソロ准将は、当初の作戦である三艦隊によるクレティナス軍の包囲作戦を支持していた。上官の身勝手で、単独の艦隊でクレティナス軍に挑むことになったが、まだ選択の余地はあったのである。だが、彼の言は不用意にもカルソリーの負の感情をあおることになった。
「君は、この私よりタイラー提督の方が優れているというのか、エンリーク・ソロ准将」
「いえ、決してそのようなことは……」
「ならば、黙っていたまえ。私はこの艦隊の司令官だ」
カルソリーの表情には明らかに不快の色があった。エンリーク・ソロにはそれがはっきりと感じられ、これ以上の自分の発言は危険だと判断させることになった。
「ハッ。失礼申し上げました、司令官閣下」
エンリーク・ソロは右手をあげて敬礼すると艦橋から姿を消した。
カルソリーは不愉快な気分を振り払うように声をあげた。
「撃て、撃て。一隻たりとも逃がすな」
帝国艦隊六○○隻の砲門が一斉に開き、収束エネルギーの粒子がクレティナス艦隊に雨のように注がれた。艦隊の前面に張られたエネルギーシールドと収束エネルギー粒子(ビーム)が衝突し、激しい閃光があがる。圧倒的な光がすべての感覚をマヒさせ、スクリーンを見つめる将兵達を緊迫が襲った。
宇宙を彩る光がクレティナス艦隊旗艦「飛龍」の指揮官席に座すアルフリート・クラインの頬を赤く染めていた。開戦後三○分にして、数で勝る千年帝国軍がヴァルソ・カルソリーの構想どおりクレティナス軍をおしていた。
「なかなか、敵もやる。秩序ある戦闘とは言えないが、たいした破壊力だ」
アルフリートはスクリーン上の帝国軍の勢いのある攻勢に感嘆した。別に困ったという表情ではない。ただ、帝国艦隊の動きを意外な眼で見ていた。
「どうやらこの艦隊には、神将タイラーはいないようですね。神将とも呼ばれる人が、このような戦い方はしないでしょう」
アルフリートと同様にファン・ラープも敵軍の動きに違和感をもっていた。決して、帝国艦隊の動きが素人のような戦闘というわけではなかったのだが、神将と噂されるタイラーの動きにしては生彩を欠くものだったのである。
「ということは敵がまだ他にいるということだ」
アルフリートは形のいいあごに手をやった。
「どうします、司令官閣下。さっさと前にいる敵さんを片付けますか」
あいかわらず緊張感のない表情をファン・ラープはしていた。本当に真剣になって戦争をしているのだろうか、この男に対しては疑問符が投げ掛けられる。戦争に真剣になる人間よりはましと言えるが、自分が生き残るための努力をしようとしないのもファンのファンたる所以であった。
「まったく随分と気楽に言ってくれるな。向こうの方がこちらより一○○隻も数が多いということを忘れて」
と言いつつも、アルフリートの表情も深刻というにはあまりにも血色のよいものであった。
戦いは帝国軍有利のまま推移していた。長距離ビームによる砲撃戦から、次第に戦艦同士が艦首を並べて戦闘機やアースムーバーを繰り出す接近戦へと移ろうとしていた。
巨大な宇宙母艦から大気圏内でも飛行可能な機動性の高いスペースファイターが発進した。火力面では駆逐艦や小型戦闘艇に劣るものの、集団で戦う場合には恐るべき力を発揮する多目的戦闘機である。また、アースムーバーと呼ばれる人型をした接近戦用機動兵器が各艦よりカタパルトによって射ちだされ、艦隊の防衛にあたった。アースムーバーはもともと対惑星攻略戦用に開発された兵器であり、戦闘機ほどの機動性はもてなかったが、内部に小型の核融合炉を有しあらゆる武器を装備できたため、攻撃力だけは戦闘機を凌駕していた。宇宙空間での戦闘では主として艦隊防衛の任にあたっていた。
アースムーバーによって発射されたビームが、戦艦に攻撃を加えようとした帝国軍の戦闘機の腹部を貫いた。直撃された戦闘機は瞬時に赤い閃光をあげて宇宙の塵と化す。戦闘機のパイロットは光とともに自分の人生の終焉を知った。
アルフリート・クラインのエメラルドグリーンの瞳に赤い閃光が映し出されていた。艦隊旗艦「飛龍」の艦橋のすぐ近くで戦闘機が爆発したのである。アルフリートは思わず片手をあげて彼を襲った光を遮断した。
「やれやれ。あぶないなあ」
「どうなさいます、司令官閣下?」
ファン・ラープ准将がにやにやしながら尋ねる。
「ここまでやられては、黙っているわけにもいくまい。そろそろ反撃するとしようか」
応えると、アルフリートはただちに視線をスクリーンに映し出される前方の敵に向けた。
「陣形を再編成。応戦しつつ凸陣形をとり後退せよ」
「あの…後退…ですか?」
アルフリートの言葉を聞き間違ったと言わんばかりに、ファン・ラープが聞き返した。
「ああ、後退だ。恒星アーメスの危険宙域ぎりぎりまで陣を退く」
艦橋を一瞬の沈黙が支配した。ベルブロンツァ恒星系は、二重太陽アーメスとラーの重力磁場の干渉によって局部的な重力異常が発生しているのである。特に恒星の近くは膨大なエネルギーが発生しており、空間の軸そのものが歪んでいた。さらに、先程からのクレティナス艦隊と帝国艦隊の戦闘によって放出されたビームのエネルギーが、付近の放射性ガスに衝突し、エネルギーの乱流を引き起こしていた。
このような中では、高度に密集した艦隊などひとたまりもない。空間歪みやエネルギー乱流に巻き込まれては戦いどころではなかった。
「司令官閣下。危険が大きすぎます。もし、敵が閣下のお考えどおり凹陣形をとり半包囲体制を敷かなければ吾が軍は壊滅の危機に陥ります」
幕僚達の表情に険しさが現われた。しかし、アルフリートはそれを軽く受け流した。
「大丈夫。敵にしてもそれが、選択できる最も効率的な戦い方だからな。それに、こちらには『ラッキー・ファン』がいる。彼の運にあやかって私は勝たせてもらうつもりだ」
「では、作戦は敵の艦隊を誘導しての中央突破、背面展開ということで」
「そういうことだ」
作戦というものは、常にその立案よりも実行に難しさがある。どのように画期的で優れた作戦であっても、実行できなければ実行可能な劣った作戦の方が上なのである。アルフリート率いるクレティナス第四四艦隊、別名「赤の艦隊」と呼ばれるこの艦隊が優れていたのは、まさにその遂行力であった。
開戦一時間後、アルフリートは艦外に出していた戦闘機、アースムーバーをそれぞれの母艦に収容すると、艦隊を編成し直し凸陣形を敷いて帝国軍に対した。一方、千年帝国軍は、クレティナス軍にあわせるように凹陣形を敷き、半包囲体制をとって構えるこになった。
|
 |
  |
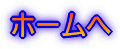
|

